更新日 2024年08月21日 | カテゴリ: キャリア・人生・仕事の悩み
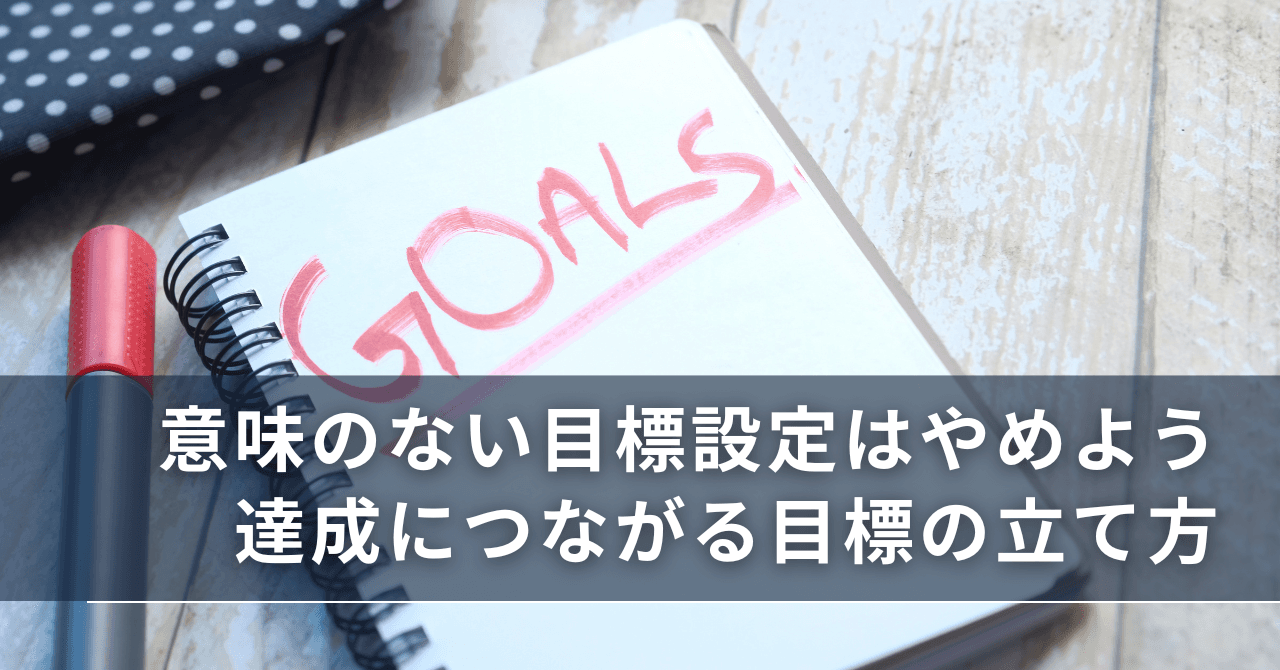
今度こそがんばろう!と目標を立てては達成できずに「自分には根性がない、目標なんて立てても意味がない」と諦めている人はいないでしょうか。
実は、目標を達成できない人は、がんばりが足りないのではなく、「良い」目標を立てるのが苦手な人なのかもしれません。
ここでは、なぜ目標設定をしたほうがいいのか、良い目標とは何かについて考察します。
人が目標を立てるのが望ましいのは、それが「今ある状態」と「ありたい姿」の差を明確にし、「ありたい姿」に近づいていくためのエネルギーになるからです。ありたい姿がどこにあるのか、そこに辿り着いたらどんな自分になれるのかを具体的にイメージすることで、より良い自分を目指すことができますし、どの道を通るのかも見えてくるのです。
現状に十分満足している人以外は,日々「もっと良く生きたい」と思いながら生きていることでしょう。不満を解消し、なりたい自分になるための効率的な方法が、目標をたてるということです。
しかし例えば「仕事ができるようになる」という目標はとても漠然としていて、その目標に対して「がんばります」という漠然とした行動プランは、行く方向や距離、具体的な目的地に関するイメージが湧きづらいので、人を動かすエネルギーになりません。
目標は立てることそのものが目的になるのではなく、自分のエネルギーになるように設定すべきです。
以下の「SMARTの原則」に従って、もっと具体的で意味のある目標を立てていくように心がけましょう。
良い目標は、以下の条件を満たしている必要があります。
曖昧で具体性を欠く目標に対して、人は行動するイメージを描きづらいものです。例えば「仕事ができるようになる」「英語が話せるようになる」といった目標ではなかなか行動につなげられませんが、「営業で上位10%以内になる」「TOEIC900点をとる」という目標であれば、達成時のイメージを抱きやすいのではないでしょうか。
目標達成に対して今どれくらい近づいているのかを測定できるものにしましょう。達成度を計る指標を決め、記録していくことが望ましいでしょう。例えば営業の獲得件数やミニテストの点数などで、達成度を常に意識しておけるようにしましょう
自分が目標達成にかけられるエネルギーやモチベーションと照らし合わせてあまりにも無理のある目標は、立てる意味がありません。目標は他人や環境の力ではなく「自分がコントロールできるリソースを使って達成できる」くらいの水準であることが大切です。
例えば TOEIC900点を目標にしたとしても、ただそのことを考えていては本来の目的を見失ってしまいます。本来は「英語を使った仕事で活躍する」というワクワクするような「本来の目的」を達成したいのであって、そのための目標がTOEIC900点のはずです。
ですから、今の目標が本来の「英語を使った仕事で活躍する」という目標につながることをイメージしておくべきで、単純に「点数を上げる」ということばかりを意識してしまうと、目的を見失ってやる気が低下してしまいがちです。
「いつかは」で行動が変わらないのは皆さん経験したことがおありだと思います。きちんと「いつまでに、これを達成する」というのを目に見える範囲で定めていくことで、具体的な行動を起こすモチベーションにつながります。
また、「◯◯しない」という目標の立て方は、具体的な行動に落とし込みづらいので、「◯◯する」という肯定的な表現を目標にするのが望ましいでしょう。
「この目標を達成したとき、自分はこんな風になっている!」というワクワクする姿を思い描きながら、具体的な行動に落とし込むことができるような目標を立てましょう。少しずつ目標に近づいている感覚が得られるはずです。
そして、「前に進んでいる」「目標に近づいている」という実感こそが、もっとがんばるエネルギーを生み出すのです。
メッセージを添えてカウンセリング体験を贈ることができるサービスです。
悩んでいる友人や家族に心のギフトを贈りませんか?
オンラインカウンセリングを受けてみたいけど、どのカウンセラーを選べばいいか分からない...
そんな時には、マッチング診断!
性格タイプ、相談内容やご希望に沿って、あなたにピッタリのカウンセラーをご紹介します。
えらべる:2つのカウンセリング方法「話すカウンセリング」「書くカウンセリング」
みつかる:220名以上の経験豊富なカウンセラー
利用された方の多くが、カウンセリングの内容に満足、または継続したいとご回答されています。