更新日 2024年08月25日 | カテゴリ: 専門家インタビュー
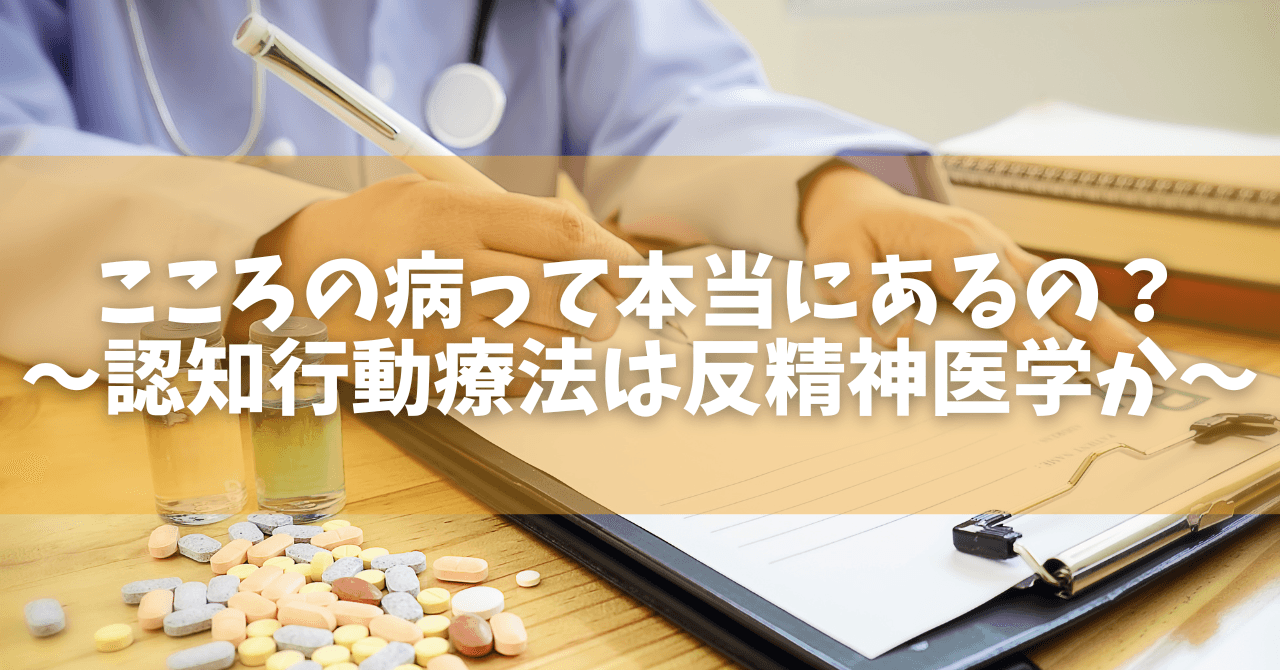
なんだか巷では認知行動療法が流行っています。こんな田舎の滋賀県の精神科・心療内科のクリニックでも「うちでは認知行動療法やってます」とか声高に書いてあったりして、いやはや困ったものです。学会でお見かけする事は無いですけどね。
まあでも、医師の診療科標榜と一緒で、認知行動療法をやってるやってないは認知ですから、本人が「うちは心療内科だ」と思えば心療内科だし、「うちは認知行動療法やっている」と思えばやっていると思ってるんでしょう。
とか書くと、反精神医学?!みたいになっちゃうのでアレですが。
さて、行動療法は一時期ケンカっぱやい時期があって、精神分析に対しても、精神医学に対しても「お前らは何にも治して無い」「行動療法だけが治療で正義」みたいなことを散々周囲にわめき散らして、ひんしゅくを買ってた時期がありました。まあ今となっては世間から認められない事に拗ねた僻みに過ぎない中二病なんですが。
ただ、私も端くれとして、その気持ちは分からなくもない所もあったりします。
それは産業カウンセリングやスクールカウンセリングでお会いするクライアントさん達で、「すぐに改善する人々」に出会った時です。そのような場面でお出会いするある種の人は(というより半分以上は)病態が軽く、大体2~3回のカウンセリングで良くなってしまうわけです。もちろんちゃんと病名はついています。診断書を得て休職していたり、学校に行けていなかったりします。
でも、数回おしゃべりしてそれなりに回復する人に病名をつける意義ってなんだろう?と思っていたわけです。これ、このまま行ったらあと一歩で反精神医学にGOです。
でもまあ、CBTセンターは医療機関からクライアントさんの紹介も多く、あんまり揉めるのもアレなので、何とか折り合えるような、いわゆる合理的認知を捻出しなければならないわけですが、今の所こんな感じに落ち着いています。
こころの病にはプロセスがあって、例えばパニック障害でも強い死の恐怖を伴う心悸亢進に代表されるパニック発作がバンバン出て燃え盛って活性な時期もあれば(割と短い期間)、その後予期不安にさらされて日常生活で回避を多くしながらも、なんとか安定している時期もある(割と長い期間)。うつ病でも今まさに!という感じで「思考制止(頭が回らない)」や「アンヘドニア(興味が沸かない)症状」が活性な期間と、それはもう済んで習慣としてうつ病の期間がある。
DSMのような「横断としての精神疾患モデル」だと、同じパニック障害、同じうつ病とせざるを得ないのですが、そのような「プロセスとしての精神疾患モデル」を考えると、すぐに良くなる人々は、すでに生物としての心の病は大方収まっていて、ただ習慣としての心の病なのです。認知行動療法が効果を発揮するのは、後者の習慣的な認知や行動に対してリハビリとしてなのです。
私はそう考えて、折り合っています。
つまり、数回で良くなる人は、「病としてはほぼ枯れているけれど、その後遺症で困っている人だった」とみなしています。だから病名も間違ってないし、私も間違ってないし、Win-Winな関係をキープできます。めでたしめでたし。
で、実際医療機関から紹介される場合でも、何となくそういう私のプロセス感と似たような感覚を持っているお医者さんだと、クライアントさんに「今はまだもうちょっと早いんだけど、お薬と休養である程度回復したら、認知行動療法というイイ心理療法があるよ」的な事を言ってくれていて、その後時期をみて実際の紹介に至ると、回復までもスムーズな感じです。(じゃあ、どこからその時期なの?それは誰にも判りません。残念な事です。)
「話が長い」「これもう全然わからん」「この人認知がオカシイから何とかして」みたいな感じで紹介されると、うーん困った・・・果たして認知行動療法がこの時期にベストチョイスな介入なのだろうか?と頭を悩ませながら、関わることになります。
ちなみに、ブリーフセラピーとか、ニューウェーブの心理療法なんかは「全ては関係性で(社会的に)構成されている」と言いがちです。たしかに心の病においてそういった側面は大きい事が否めないのですが、やはりそれは全てではないと感じています。どんなに短い期間であれ、社会的に構成されたものとは別に、やはり病的な体験は存在しています。それは本人にとって、いかんともしがたいわけです。
利得を求めて疾病になる人は中々いないわけで、望まない疾病を得て、それが不必要に長引いてしまった時、自然と社会の中で何らかの機能をまとい始めたというのが実際の所だと思います。ただ我が国の数年単位のDUP(精神病未治療期間)から言って、ほぼ100%社会に取り込まれた状態でクライアントさんとお出会いする事となるでしょう。
あとは、何でしょうかね。別室登校が、やがて教室登校を阻害し、デイケアやリワークが、やがて社会復帰を阻害するように、良く構成された認知行動療法が本来数回で良くなる人を却って長引かせることは多いにある可能性でしょう。
もちろんお薬では治らないような習慣をお薬で治そうとし続ける限り、こころの病は終わりなき慢性疾患になるでしょう。
少ない回数で何とかなる人にはそれなりに、何回もかかる人にもそれなりに、回復のジャマだけはしたくないものです。
メッセージを添えてカウンセリング体験を贈ることができるサービスです。
悩んでいる友人や家族に心のギフトを贈りませんか?
オンラインカウンセリングを受けてみたいけど、どのカウンセラーを選べばいいか分からない...
そんな時には、マッチング診断!
性格タイプ、相談内容やご希望に沿って、あなたにピッタリのカウンセラーをご紹介します。
えらべる:2つのカウンセリング方法「話すカウンセリング」「書くカウンセリング」
みつかる:220名以上の経験豊富なカウンセラー
利用された方の多くが、カウンセリングの内容に満足、または継続したいとご回答されています。