更新日 2024年08月25日 | カテゴリ: 専門家インタビュー

マインドフルネスは、近年、瞑想法のひとつとして多方面から注目を集めています。
今月「ケアする人も楽になるマインドフルネス&スキーマ療法」を執筆され、国内における認知行動療法とスキーマ療法の第一人者である伊藤絵美先生に、マインドフルネスの効果と意義について伺いました。
<後編:根本的な「生きづらさ」と向き合うスキーマ療法|臨床心理士 伊藤絵美>
ストレスと付き合うセルフケアの方法として認知行動療法がありますが、マインドフルネスは、その『土台』なんです。マインドフルネスというのは、「今、ここ」の体験から生まれる感覚を、大切にできるようになることです。
私は、二十数年間認知行動療法に関わってきて、認知行動療法の中で一番重要な要素は、セルフモニタリングだと思っています。
自分にとって何がストレッサーになっているのか、どんな自動思考がでてきて、どんな感情が生まれて、体がどんな状態か、それに対してどんな行動をとっているのかにまずは「気づく」ということ。
巷では認知行動療法といえば『認知の歪みを直す』とか『行動を修正する』というイメージを持たれることが多いんですが、「内的な体験に気づく」ということが一番重要なんです。
それができれば、認知や行動を無理やり変えようとしなくても、回復していくんですよ。ストレスと付き合うためにはセルフモニタリングが大事で、それはマインドフルネスで行うこととほとんど同じです。
例えばうつ病の人は、自分の体験や思考、行動、反応に気づくと、それをまた責めてしまう、というサイクルに入ってしまいます。こんな風に考えちゃうなんて、とか、こんなことで落ち込むなんて、自分は良くない人間だ、と、さらなる自分責めを始めてしまうんです。
それはすごくもったいないことです。自動思考や気分・感情は自然に出てくるもので、あ、自分はこういう気持ちになってるんだ、ということを受け止めればいい話。自分の気分に気づいて、観察して、それを価値判断せずに受け止める態度がマインドフルネスです。
ここがしっかりできると、これ以上の認知行動療法の技法を使わなくても、自分に優しくできるようになります。
自分に優しくできるということは人にも優しくなれるということです。受け止めたうえで、自動思考や感情に流されることなく、適切な行動がとれるようになるんです。
ビジネスの世界のマインドフルネスは、『〜のために』という『目的意識』が入ってしまいますよね。
悪いとは言わないけれど、例えば『生産性を上げるため』『落ち着きを取り戻すため』の『スキル』として捉えられている面が大きいような気がします。
『ためになるかならないか』と考え始めた瞬間に、価値判断が入ってしまい、それは定義上マインドフルではなくなる。つまりマインドレスになってしまいます。
一方で、マインドフルネスってもともとは仏教の考え方ですね。
おととし、ティクナットハンという有名な仏教者がつくっている共同体の方々がワークショップに来てくださったんですが、その方達にとってはマインドフルネスは生き方そのものなんです。その人たちは目つきも澄んでいるし、見た瞬間に違う、という感じがします。
スピリチュアル・宗教的なマインドフルネスがある。
サマタ瞑想とか、ヴィパッサナー瞑想など、様々な種類の瞑想がありますが、体験を重ねていくにつれ、マインドフルな状態も変化していきます。
マインドフルネスに関する脳の研究でも、初心者の脳と熟達者の脳の状態は違うことがわかっています。

でも私たちには生活もあるし。『何かの目的を前提としたマインドフルネス』というのと『生き方そのものとしてのマインドフルネス』という世界観の両極端の間で生きていますよね。
だから、私たちはその間で『世界と自分をよりしっかり感じるための生活技術』とか『生活を豊かにするための実用的技術』としてのマインドフルネスを実践していくのが良いのではないかと思っています。
結果として生活が豊かになったり、自分がしっかりしていくような実感が生まれていく、ということなのではないでしょうか。
マインドフルネスを一番必要とするのは、自分の感情に触れないように生きてきた人たちです。自分の内的な体験を無視して生きている人。
そのまま生きていける人もいるけど、それだと生きづらくなってくることもあります。
この本の主人公は『傷付いた人』ですが、そもそも傷ついていることにすら気づけない人たちも多いんですよね。
社会人に多いのは、外側の課題を解決することばかりを意識して、自分の内面や思考・感情には鈍感になってしまっている。
こういう方にマインドフルネスの概念をお伝えしても、すぐに「なるほど」とはならずに、いらいらしてきたりするんです。こんなことをやって何になるのか、と即効性を求めてくる。
こういう方にこそ、辛抱して取り組んで、内的な感覚を取り戻して欲しい、と思います。
マインドフルネスを身につけることは心理的なメタ認知能力を上げるということでもあります。自分を見るもう一つの視点が定まり、自動思考や感情に振り回されなくなります。
やはり感じているものを感じないようにする、というのは不健康だし、不自然だと思いませんか。
ネガティブな感情は、生きて行くのに必要なものです。不快な感情を人がなぜ持っているかというと、良くないことが起こるぞとか、生命を脅かすことがあるぞというシグナルですよね。そんなシグナルを感じないようにしていれば、必要なサインも見逃してしまうかもしれない。
それに、ネガティブな感情を抑えるているということは、ポジティブな感情も抑えている、ということです。
感情を抑えて、生々しい感情をなかったことにして生活するのは不健康。感情を感じつつも、それに振り回されないことが大切です。
内的な体験に気づくことが、生きている、という感覚につながり、自分にとってより良い行動にもつながっていくはずです。
私自身も、ネガティブ・ポジティブ両方の感情が生き生きしてきたことを感じています。
食べ物が喉を通っていくときの感覚、飲み込んだ後の余韻、水の味わい、ひとつひとつの生活の中の行いが、ありがたいものに変わっていく感じがあります。
わかりやすい変化としては、家事が嫌いじゃなくなりました。
皿洗いひとつをとっても、マインドフルに行うと、お皿の重さとか、お湯の温かさ、泡の感じ、油の残り方、手触り、すべてがマインドフルな体験になります。それまでは、イライラしながらやっていたんですけどね(笑)。
あまり遠くから見すぎると感情を押しやって虚無につながってしまいます。距離感の問題ですね。遠ざけ過ぎずに、『ガン見する』イメージでしょうか(笑)。
1〜2年はかかると思います。
私自身も、マインドフルネスを自分のために実践しようと決めて、マインドフルネスを意識して生活できるようになって、生活の中に根付いたと感じるのは2〜3年かかっているんです。
この本にもいくつかのワークが出ていますが、その中から選んで、とにかく毎日続けることです。リマインダーを設定して、とにかく毎日続けてください。
やはりセラピストと一緒にやるのが実感もしやすいんですが、もちろん一人でも身につけることはできます。実際我々は自分でやっていますしね。
ちなみにセラピストと一緒にやる場合には、きちんと自分自身でマインドフルネスに取り組んで、マインドフルネスの体験を自分のものにしている人と行ってほしいですね。
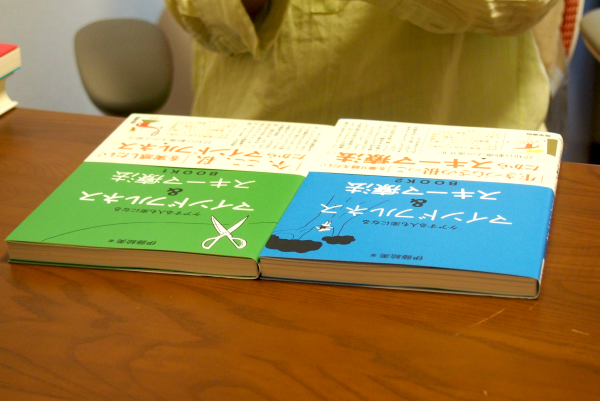
◉ケアする人も楽になる マインドフルネス&スキーマ療法 BOOK1(医学書院)
◉ケアする人も楽になる マインドフルネス&スキーマ療法 BOOK2 (医学書院)
メッセージを添えてカウンセリング体験を贈ることができるサービスです。
悩んでいる友人や家族に心のギフトを贈りませんか?
オンラインカウンセリングを受けてみたいけど、どのカウンセラーを選べばいいか分からない...
そんな時には、マッチング診断!
性格タイプ、相談内容やご希望に沿って、あなたにピッタリのカウンセラーをご紹介します。
えらべる:2つのカウンセリング方法「話すカウンセリング」「書くカウンセリング」
みつかる:220名以上の経験豊富なカウンセラー
利用された方の多くが、カウンセリングの内容に満足、または継続したいとご回答されています。