更新日 2024年08月25日 | カテゴリ: 自分を変えたい
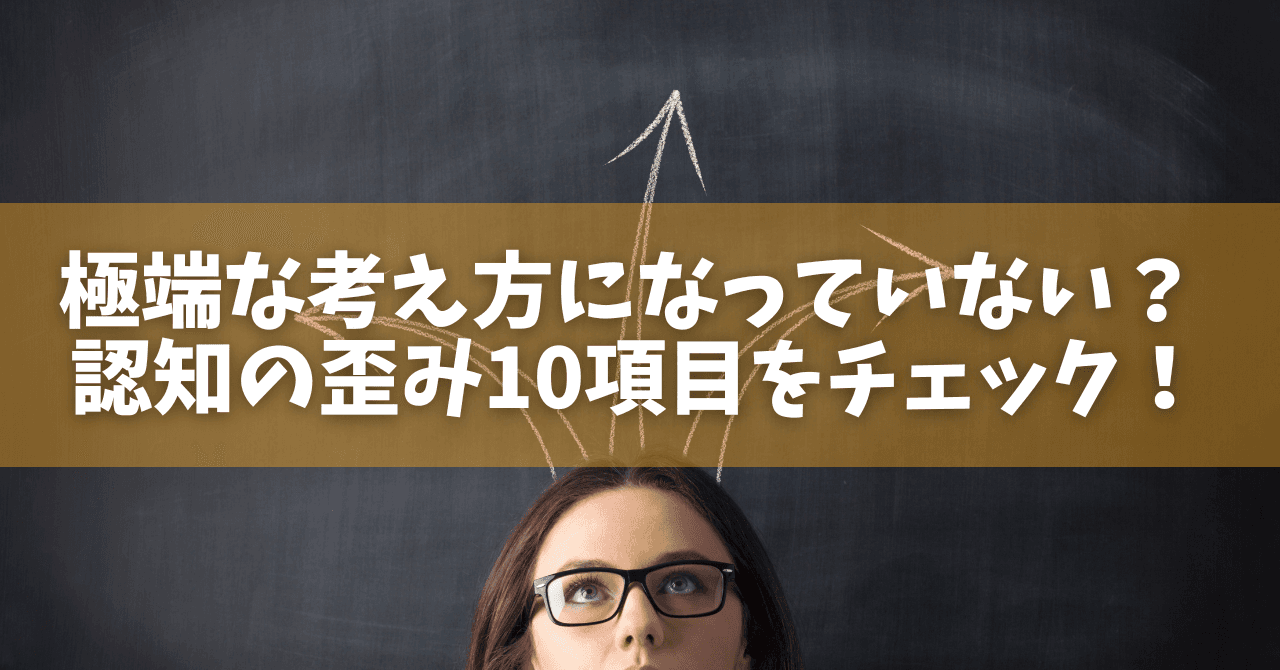
「認知」とは出来事に対して浮かんでくる考えのこと。だから同じ出来事に出会ってもポジティブに考える人もネガティブに考える人もいますし、その後の行動も変わってきます。
極端に偏った考え方で出来事をネガティブに捉えている状態を心理学用語で「認知の歪み」と言います。そして「認知の歪み」が習慣になると「自動思考」と呼ばれる思考に陥り、客観的に出来事を捉えることができず、知らず知らずのうちに自分を苦しめていく危険性もあるのです。
今回は「認知の歪み」には具体的にどんなものがあるか、そして「認知の歪み」が生じる原因と改善方法についてご紹介します。
まずは認知の歪み10項目をご紹介します。自分に当てはまるものはないかチェックしてみましょう。
「白黒思考」とも呼びます。少しのミスも許せない完璧主義者で、テストで90点を取ったとしても、ミスした10点が気になり「全然ダメだ!」と感じてしまいます。そのため、自分を責めることが多くなります。
また、他者のダメなところも許せないため、勝手に幻滅して関係を切ってしまったり、ミスを責め立ててトラブルに発展してしまったりすることがあります。
「2度あることは3度ある」ということわざがありますが、「一般化のしすぎ」では「1度あることはこの先ずっとある」という思い込みに囚われてしまいます。
例えば、テストでたまたま良い成績が取れなかった時には「私は勉強ができないんだ」と思い込んでしまいます。
まるで心にフィルターを貼ったように出来事の良い面を遮断して、悪い面だけを取り入れる考え方です。
テストで良い成績を取ってみんなが褒めてくれても、たった1人の「こんな成績じゃダメだ」というネガティブな言葉だけが強く残ってしまい、次に行動するのが怖くなってしまいます。
マイナス化思考はプラスになるはずの良い出来事を、自分の中でマイナスの出来事に置き換えてしまう考え方です。
例えば、英語のテストで良い成績を取っても、「でも数学は悪いから意味がない」と考え、確かにあるはずのプラスの事実を打ち消してしまいます。
他者の気持ちを勝手に想像して、「こう思っている」と決めつけてしまう考え方です。
例えば、テストの点数を友人に教えた時に「へぇ」と言われただけで、「バカにされているんだ!」と勝手に結論づけてしまいます。実際にはバカにされていなくても、そう思って接するため、友人との関係がぎくしゃくしたものになってしまいます。
失敗を大きく、成功を小さく見てしまう考え方です。
テストで平均点より10点良い点数を取ったとしても「たった10点だけか」と感じるのに、平均点より10点悪い点数を取ったときには「10点もミスした!」と感じてしまいます。
感情を理由に出来事の意味を決めつけてしまう考え方です。
例えば、テスト前の不安を根拠に「こんなに不安になっているんだから、このテストは失敗するに違いない」と思い込んでしまいます。
明確な根拠があるわけではないのに「〇〇すべき」という信念で自分や他者を苦しめてしまう考え方です。
心や身体の不調より「テスト前は勉強すべき」という信念が重要視されるため、知らず知らずのうちにストレスや疲労が蓄積されていきます。
自分に悪いレッテルを貼ってしまう考え方です。「どうせ自分はダメだから」「自分なんて無価値な人間」と決めつけてしまいます。
レッテルを貼ることで、最初から行動を諦めてしまったり、失敗したときにその原因を探すのではなく「自分はダメだから」で片づけてしまったりするため、成長することができず、ますますレッテルが強固なものになってしまいます。
悪い出来事の原因はすべて自分に責任だという考え方です。
先生から「このクラスの平均点が1番悪かった」と言われたときに「自分の成績が低いせいだ」と、さも全てが自分のせいだと感じるような状態です。
認知の歪みが生まれる原因としては、育ってきた環境や文化が大きく影響しています。
親や先生など周囲の大人からの教えが、いつの間にか認知の歪みとなっている場合もあります。
また、認知の歪みは失敗や傷つきから自分を守る方法でもあります。
「マイナス化思考」や「レッテル貼り」で自分を批判しておくことで、他者から批判を受けるショックを和らげることができますし、「心のフィルター」や「拡大解釈と過小評価」で失敗する可能性のある出来事を敏感に察知することで、失敗を避けるように行動することができます。
適切かどうかは別として、その認知の歪みはあなたを守ってきたのです。
発達障害をもつ方は、その特性として「全か無かの思考」が強い傾向にあります。
また、障害という診断はなくとも、人には大なり小なり特性があります。その特性が認知の歪みに与える影響も少なくありません。
認知の歪みは認知行動療法を使ったカウンセリングを活用することで改善することができます。また、自分で本を参考にしながら改善していくことも可能です。
ただし、自分で自分を客観的に見つめる作業はなかなか難しいものです。最初はカウンセラーなど専門家に手伝ってもらい、コツをつかんだうえで本などを通して自分で改善する練習を重ねた方が効果的です。
誰でも認知の歪みは持っているため、全てを改善しなければならないわけではありません。
ただし、その歪みが自分を苦しめるほどに大きくのしかかっているのに放っておくと、うつ病をはじめとした心の病気を引き起こすリスクがあります。
負担となっている認知の歪みは改善することで、視野が広がり柔軟に生きられるようになっていきます。
「認知の歪み」は気づかないうちにかけている色眼鏡です。色眼鏡越しに自分がかけている色眼鏡の色に気づくのは意外と困難な作業です。また認知の歪みはあなたを守っている部分もあるため、ストレス場面に対処する別の方法なども探しておく必要もあります。
cotreeには認知行動療法の専門家も在籍していますので、ぜひ活用してみてください。
メッセージを添えてカウンセリング体験を贈ることができるサービスです。
悩んでいる友人や家族に心のギフトを贈りませんか?
オンラインカウンセリングを受けてみたいけど、どのカウンセラーを選べばいいか分からない...
そんな時には、マッチング診断!
性格タイプ、相談内容やご希望に沿って、あなたにピッタリのカウンセラーをご紹介します。
えらべる:2つのカウンセリング方法「話すカウンセリング」「書くカウンセリング」
みつかる:220名以上の経験豊富なカウンセラー
利用された方の多くが、カウンセリングの内容に満足、または継続したいとご回答されています。