更新日 2024年08月29日 | カテゴリ: 子育て・家族関係
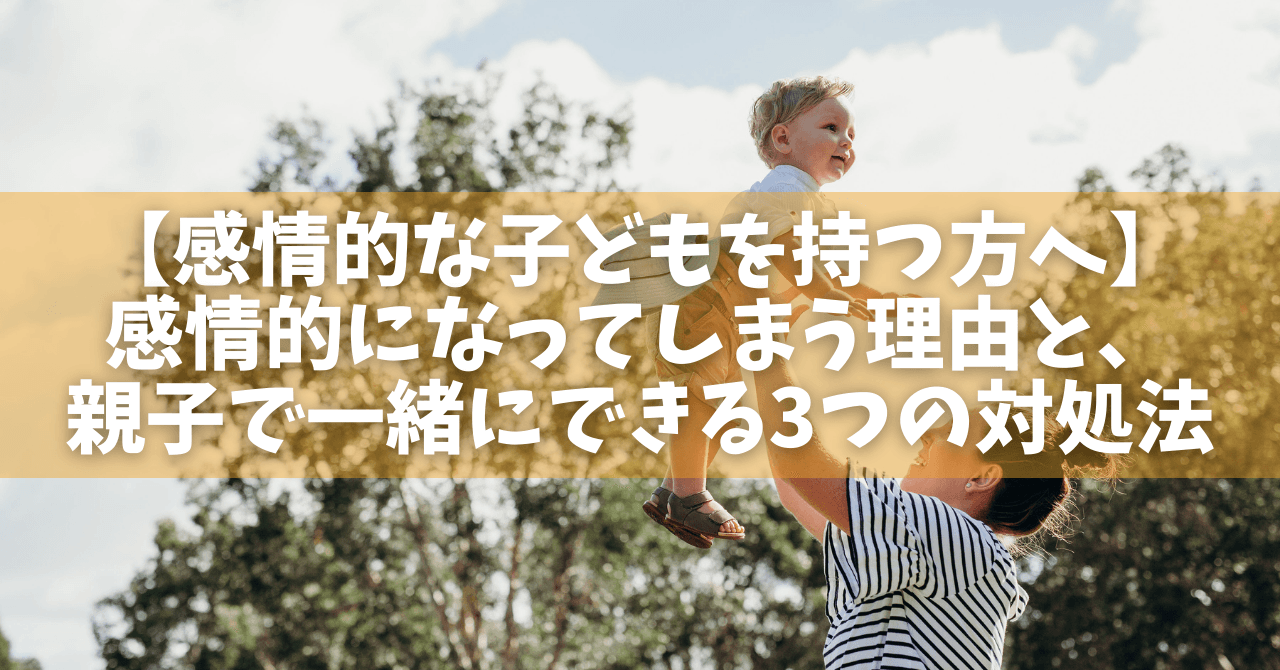
「うちの子、すぐにキレてしまって困る」
「一度感情的になると、手がつけられなくて…」
小さな頃であれば「小さいのだから仕方がない」と許容してきた感情の爆発が成長をしても治らない、親としてどうやって対応をしていいのか…このような悩みを抱えるケースは、現在増えていると言われています。
中には、「なんでこんなに育てづらいのか」と、子供を厭う気持ちを抑えきれずに悩む親御さんもいるほどです。
しかし感情のコントロールができないことで苦しんでいるのは、親の側だけではありません。
キレる・暴れる子供たち本人も、大きな苦しみを抱えて日々を過ごしているのです。
ここでは感情的になってしまう子供たちの心の背景と、親と家族がこれから一緒に行っていける歩みについて解説をしていきます。
子供たちは大人達に比べ、ありあまる生命力を抱えています。
例えばほんのすこしの移動でも子供たちは力いっぱいに全力疾走をしますし、たった10分の休憩時間でも精一杯に遊びますよね。
体の力も心の力も、常に活動を求めている状態なのです。
ところが現代社会においては、このようなエネルギーを発散する場がどんどん少なくなっています。
大きな声を出して遊べる場は年々減っていき、子供同士だけで走りながら遊び回ることも都市部では難しくなりました。
「ゲームをしていればおとなしいから」「スマホの動画やテレビを見せておけば静かにしていられるから」等、子供をいかに静かにさせておくか、おとなしくさせておくかが育児における重要な要素となってしまったのです。
エネルギーの発散場所の無い子供たちは、次第にストレスを抱えていくようになります。
何か不満となることが起こった時、溜め込んだエネルギーや抱えたストレスが一気に爆発してしまうのです。
現代社会では「個性を重視した幼児教育」が求められていますが、実際には子供たちの感情や個性は抑圧されがちで、画一的なロールモデルが強いられていると言わざるをえません。
例えば「ケンカを絶対にしない・させない」という方針も、ひとつの抑圧と言えるでしょう。
お互いの欲望が違うが故に起こる「ケンカ」とは、子供がコミュニケーションを学ぶ上での大切なステップです。
しかし近年では、「子供には『優しい良い子』でいて欲しい」という思いから、早期段階でケンカを終わらせてしまう(お互いに謝らせる)といった対応を行うケースが増えています。
もちろん、ケンカが激化をすれば先生や親が仲裁に入る必要もあるでしょう。
ただ、心の中に大きな不満を抱えたままで「ゴメンナサイ」とお互いに誤ったところで、怒りや不満と言ったネガティブ感情が消え去るわけではありません。
それでも「親には愛されていたい=良い子でいなくてはならない」という思いから、子供たちはネガティブな感情を抑圧し続けていくのです。
このような抑圧・プレッシャーが、「キレる子供」を生む大きな要因となっています。
社会の変動による貧困も、子供たちの心には大きな影を落としています。
生活に余裕が無ければ、親たちは子供にゆっくりと向き合う時間を作ることもできません。
更に経済的な苦境にあれば家族達の心の余裕も減ってしまい、刺々しいやりとりや乱暴な言葉づかいが増えることもあります。
親たちのピリピリとした空気を子供たちは如実に感じ取り、不安や不信感を抱え続けることになるのです。
現代日本社会で強く見られるようになった傾向が、「強い完璧性を求める」というものです。
例えばコンビニに行った時、ファミレスで食事をした時…店員さんに何かミスがあったりすると、「教育が行き届いていない」と強く怒ったり、不満を家族内でも長々と言い合うといった傾向が見られるようになっています。
そこまで大きな実害を被ったわけではなくても、「完璧でなくてはならない!」という理想を他者に求めるようになっているのです。
しかしこのようなパーフェクト志向とは、すなわち「減点方式」ということになります。
欠けている部分にばかり目が行き、相手の「良い部分」を探さなくなっていくのです。
これは家族同士の評価にも影響を与えますし、最終的には自分に対しても「減点方式」を行うようになっていきます。
「どうして完璧ではないんだ!」という怒りが生まれる根本には、「完璧でなくてはならない」という強迫観念があるのです。
家族などの「内側の人」に対してはもちろんですが、自分達を取り巻く周囲の人達に対しても「完璧であれ」という考え方を持つのを止めていきましょう。
人間は誰しも、怒りや哀しみといったネガティブな感情を持つものです。
いつもニコニコと楽しく過ごせていたら確かに素敵ですが、子供達に「常に笑顔であれ」という強制を行えば、強い抑圧を生むことになります。
怒り・哀しみ・不満…このような感情が子供たちに生まれた時に、「一刻もはやくその感情を抑えよう」とするのは禁物です。
「怒るな/泣くな」と言われれば、子供たちは感情を抑圧し、より大きなストレスを抱え込みます。
まず一度は、不満はどこにあるのか、哀しみがどこにあるのかを聴き、そのネガティブ感情に対して共感を示してあげましょう。
そして一緒に「どうしたら問題を解決していけるのか」を考えていくことが大切なのです。
強い感情抑圧やストレスを抱え続けた子供たちの中には、物事の受け止め方(認知)に歪みが生じてしまっているケースが多く見られています。このような認知の歪みに対しては、カウンセラーなどの専門家による対処(行動認知療法等)が必要となります。
「子供の苦しみをわかってあげられていないかもしれない」「家族の中だけで対処をするのが難しい」と感じたら、専門家に相談をしてみましょう。
ネガティブな感情のコントロールができない、自分の欲求が抑えきれずに人間関係がうまく構築できない…このような問題は、今後の精神的な成長の大きな妨げともなります。
問題を改善できないままに成人し、いわゆる「キレる大人」となってから社会生活に支障があることを感じて専門医を受診する人も少なくありません。
家庭内での対処が難しい場合には、「子供の問題は親だけで対処しなくては」という思い込みを手放し、早めに専門医・カウンセラーへの相談をすることも大切です。
メッセージを添えてカウンセリング体験を贈ることができるサービスです。
悩んでいる友人や家族に心のギフトを贈りませんか?
オンラインカウンセリングを受けてみたいけど、どのカウンセラーを選べばいいか分からない...
そんな時には、マッチング診断!
性格タイプ、相談内容やご希望に沿って、あなたにピッタリのカウンセラーをご紹介します。
えらべる:2つのカウンセリング方法「話すカウンセリング」「書くカウンセリング」
みつかる:220名以上の経験豊富なカウンセラー
利用された方の多くが、カウンセリングの内容に満足、または継続したいとご回答されています。