更新日 2024年08月23日 | カテゴリ: ストレスに対処したい
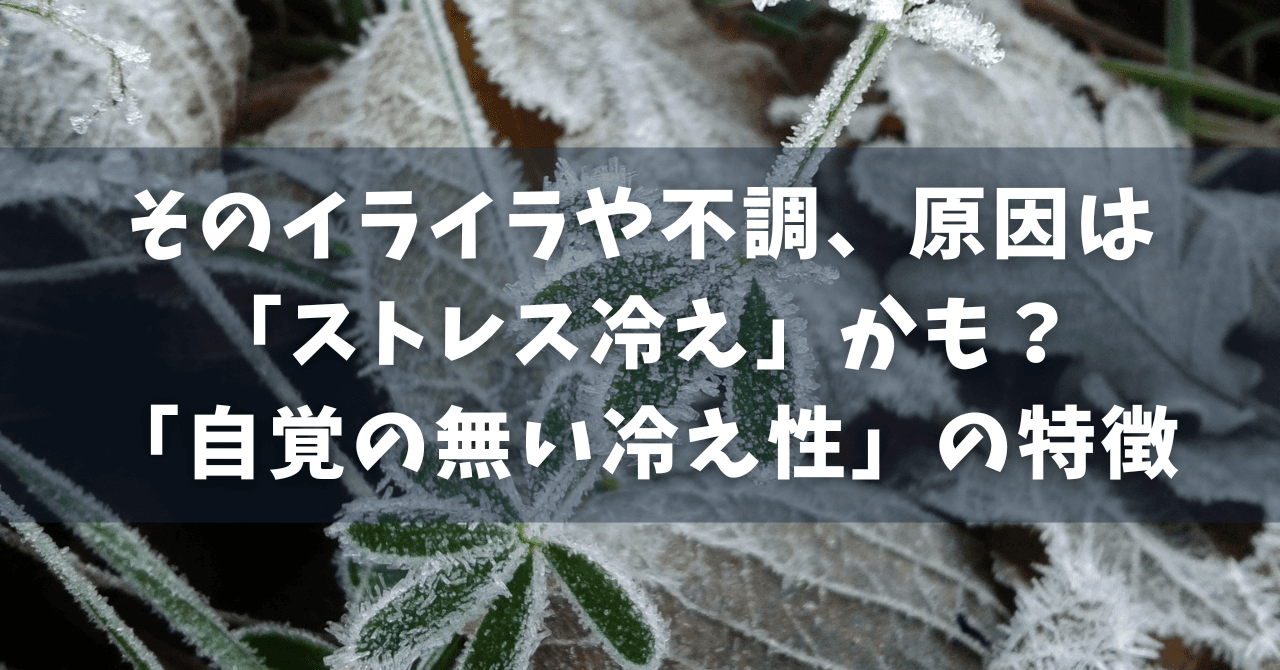
「最近、イライラした気分がおさまらない」 「夜によく眠れなくて、朝起きてもボンヤリしてしまう…」 理由のよくわからないイライラや不眠等の症状を訴える人の数は、年々増えていると言われています。
その原因のひとつとして考えられているのが、「ストレス」を原因とした体の冷え。 一般的な冷え性とは異なり体が冷えている自覚が無いことも多く、エアコンの効いた7月頃~9月頃に強く体を冷やしてしまい、夏~秋にかけて気分の不調を訴えるケースが多いのです。 今回は「ストレス冷え」の原因や特徴、対策について解説をしていきます。
人間の体の血行や心肺機能を司っている「自律神経(交感神経/副交感神経)」。 体に汗をかかせて体温を下げる等、体温調整の役割も果たしている重要な神経です。
この自律神経は人間の感情とも強く連動しており、緊張状態では交感神経、リラックスした状態では副交感神経が主に働いています。 ところがストレスがかかる状態が長く続くと交感神経が活発になりつづけ、副交感神経との切り替えスイッチが正常に作動しなくなってしまうのです。 カンタンに言うと「体が常に緊張した状態」となってしまうのですね。
こうなると人体は体温調整がうまくできなくなり、血行の滞りによって内蔵等が冷えてゆくようになります。 この「冷え」によって更に自律神経のスイッチをうまく作動しなくなり、イライラや不眠、食欲不振、抑うつ症状等の身体的問題を引き起こすのです。
夏場の暑い場所に居ても自律神経がうまく働かず、汗をかきにくくなっている状態です。 汗をかく習慣が無い状態だと汗腺の機能が低下しており、汗をかいてもベタついた汗になることもあります。
ストレス状態では交感神経が過剰に活発になり、てのひらや足の裏、ワキ等には汗をかきやすくなります。
お腹のへその下あたり(丹田)や腰に手のひらで触れた時に「冷たい」と感じる場合には、体の末端よりも内蔵が冷えてしまっている状態です。
一般的な冷え性とは異なり「冷えている」という感覚が少なく、またストレス等から砂糖・アルコール等の嗜好品の摂取を求める傾向が見られます。 アイスコーヒー・ビール・アイスクリーム・ジュース等の体を冷やす製品を頻繁に摂取し、内蔵をますます冷やしてしまいます。
上着を着る、靴下を履くといった一般的な「外側からの冷え対策」を行うと体温がこもったように感じ、余計に不快感(イライラ)を感じる傾向も見られています。
「もしかしてストレス冷えかも…」と思ったら、自律神経のバランスを整える以下の3つの対策を行ってみましょう。
ストレス冷えの人がいきなり温かい食べ物や飲み物に切り替えると、体温の急上昇に慣れずに却って不快感を覚えることもあります。 まずは血行を良くして体の内側からゆっくりと体を温める食材を多く取り入れるようにしましょう。
・ねぎ
・ショウガ
・かぼちゃ
・ごま
・シソ
上記のような薬味系の食べ物は普段の食卓にも取り入れやすく、手軽に体を温めてくれます。 また生で食べられる野菜を避け、根菜類を主に食べるようにしましょう。
パソコンやスマホの画面を凝視していると、視神経が受けた光で交感神経が活発に働き、緊張状態/興奮状態が継続してしまいます。 副交感神経へのスイッチを促すためにも、パソコン・スマホは夜には早めに終わらせて、照明を暗めに落とした部屋でゆっくりと過ごしましょう。
運動不足も自律神経を失調させる要因のひとつです。 ウォーキング等のごく軽い運動でOKですので、週2~3回程度といった定期的な運動の時間を持つようにしましょう。 また夜の入浴後等に軽いストレッチを行うことも体をリラックスさせ、冷えを予防してくれます。
ストレスによる体の冷えは身体的な不調だけでなく精神的な不調も悪化させやすいため、元々持っていたストレスが更に溜まりやすくなる…という悪循環になることも。 「たかが冷え」と侮ることなく、早めに対策をスタートしておきましょう。
メッセージを添えてカウンセリング体験を贈ることができるサービスです。
悩んでいる友人や家族に心のギフトを贈りませんか?
オンラインカウンセリングを受けてみたいけど、どのカウンセラーを選べばいいか分からない...
そんな時には、マッチング診断!
性格タイプ、相談内容やご希望に沿って、あなたにピッタリのカウンセラーをご紹介します。
えらべる:2つのカウンセリング方法「話すカウンセリング」「書くカウンセリング」
みつかる:220名以上の経験豊富なカウンセラー
利用された方の多くが、カウンセリングの内容に満足、または継続したいとご回答されています。