更新日 2024年09月03日 | カテゴリ: 職場のメンタルヘルス
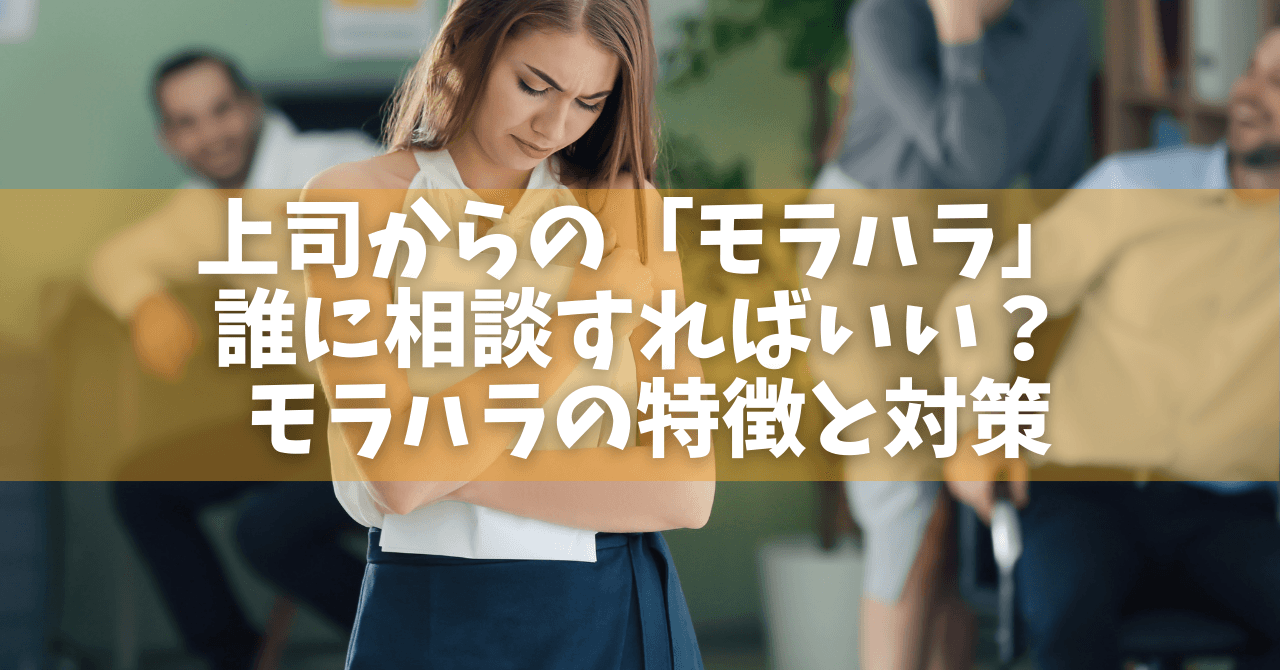
近年「パワハラ」と共に話題になっている「モラハラ(モラルハラスメント)」。 特に会社でのモラハラによるストレスで心身のバランスを崩す人が増えており、モラハラ対策の推進が叫ばれるようになっています。
しかし「セクハラ」「パワハラ」に比較すると「モラハラ」についてはその内容を知っている人が少なく、企業側も意識が低いのが現状です。 ここでは職場におけるモラハラについて、その特徴やモラハラ対策を解説していきます。
モラハラとは精神的な暴力や嫌がらせを指す言葉です。 しかしこれだけだとちょっとわかりにくいところがありますね。 まずは職場におけるどのような行為が「モラハラ」にあたるのかをチェックしていきましょう。
・無視
・意識的な阻害(仲間はずれ)
・被害者当人の発言後に鼻で笑う
・被害者当人との会話後に溜息をつく
・被害者当人の発言中・電話中等に大声で別の話を始める
・被害者当人の発言後に必ず揚げ足を取る
・すれ違いざま、挨拶時等に誹謗中傷する
・話し合いをしようとしてもはぐらかされる
「パワハラ(パワーハラスメント)」の場合、その加害者は上司や男性といった権威・力を持つ側であり、被害者は部下・女性といった力・立場の弱い側です。 パワハラ行為は恫喝や仕事の取り上げといったものになり、周囲にも「パワハラが起きている」という認識がしやすくなります。
ところが「モラハラ」の場合、パワハラのような権威・立場(パワー)を使ったハラスメントではありません。 例えば実際のモラハラ事例では、パートの人たちが一斉に上司一名を無視するといった「部下から上司」「同僚同士」といったケースも散見しています。
またパワハラのような肉体的暴力、威嚇行為、罵声・罵倒といった表面化しやすいものではなく、一見すると双方にコミュニケーションが取れているようにも見えることもあります。
1 )職場内のどのような立場の人でもモラハラ加害者・被害者になりうる(上下関係の必要が無い)
2 )内容が陰湿で表面化しにくく、周囲がモラハラに気づきにくい
3 )加害者側が被害内容を軽視していることが多い
上記の職場でのモラハラチェックリストを見て「もしかして?」と思うところが多ければ、モラハラ被害に遭っている可能性も大。 一人で悩む前に、モラハラ対策を開始してみましょう。
パワハラ・モラハラ等のハラスメントについては「どんなことが行われたか」という実際の内容・証拠をできるだけ正確に取ることが重要です。
いくら主観的に「辛かった、悲しかった」という話をしても、「いつ・どこで・誰によって・何が行われたのか」がハッキリしないと、ハラスメントの立証が難しくなります。
・年月日/時間/内容を手書き記録で収める(デジタルデータよりも改ざんが少ないため証拠記録の信用度が上がります)
・ボイスレコーダーでの録音
・私物が壊れているといった場合には写真での記録
・SNS・メール等での会話の場合、スクリーンショットを記録
特に業務に支障が出た場合には、その点も詳細に記録しておいてください。
一定の記録を取ったところで、可能であればまず上司(管理監督者)に相談を行います。 ただし上司自身がモラハラ加害者である場合や、直属上司がモラハラに対する認識が低い場合には、企業内のハラスメント相談窓口に相談しましょう。
モラハラのストレスによって心身に異常が起きている場合には、産業医へ相談をしてみるのも良いでしょう。メンタルヘルスに強い産業医であればモラハラ対策についても親身に指導を行ってくれます。また産業カウンセラーと提携している企業では、モラハラについてのカウンセリング対応も行っています。
企業内での相談が難しい場合には、外部機関への相談を行います。厚生労働省による相談窓口(都道府県労働局)の他、パワハラ・モラハラに強いNPO・NGOや弁護士会に相談してみるのも良いでしょう。 またモラハラによってうつ病や適応障害といった心の病気の症状が見られている場合には、心療内科・精神科等の専門機関を受診してください。
「会社でのモラハラ」に限らず、モラルハラスメントは被害者・加害者同士のみでの解決を行うのが非常に困難となっています。 加害者側に罪の意識が無い/意識が軽いため、被害者がガマンをしても言い返しをしても問題がより拗れてしまうことが多いのです。
モラハラの事例・証拠をより多く正確に集め、第三者に相談をすることが大切になります。
ただしモラハラによるストレスで既に心身に症状が出ている場合には、まずは心のバランスを取り戻しましょう。 相談できる場所が無い、専門機関への受診に抵抗がある場合には、メールカウンセリング等のオンラインカウンセリングからスタートするのも手です。
多くの悩みをサポートしてきた実績をもとに、一人ひとりに寄り添い、組織の生産性向上につなげます。
カウンセリングをベースに、コーチングやメンタルヘルス研修まで幅広いご支援が可能です。
えらべる:2つのカウンセリング方法「話すカウンセリング」「書くカウンセリング」
みつかる:220名以上の経験豊富なカウンセラー
利用された方の多くが、カウンセリングの内容に満足、または継続したいとご回答されています。