更新日 2024年09月03日 | カテゴリ: 職場のメンタルヘルス
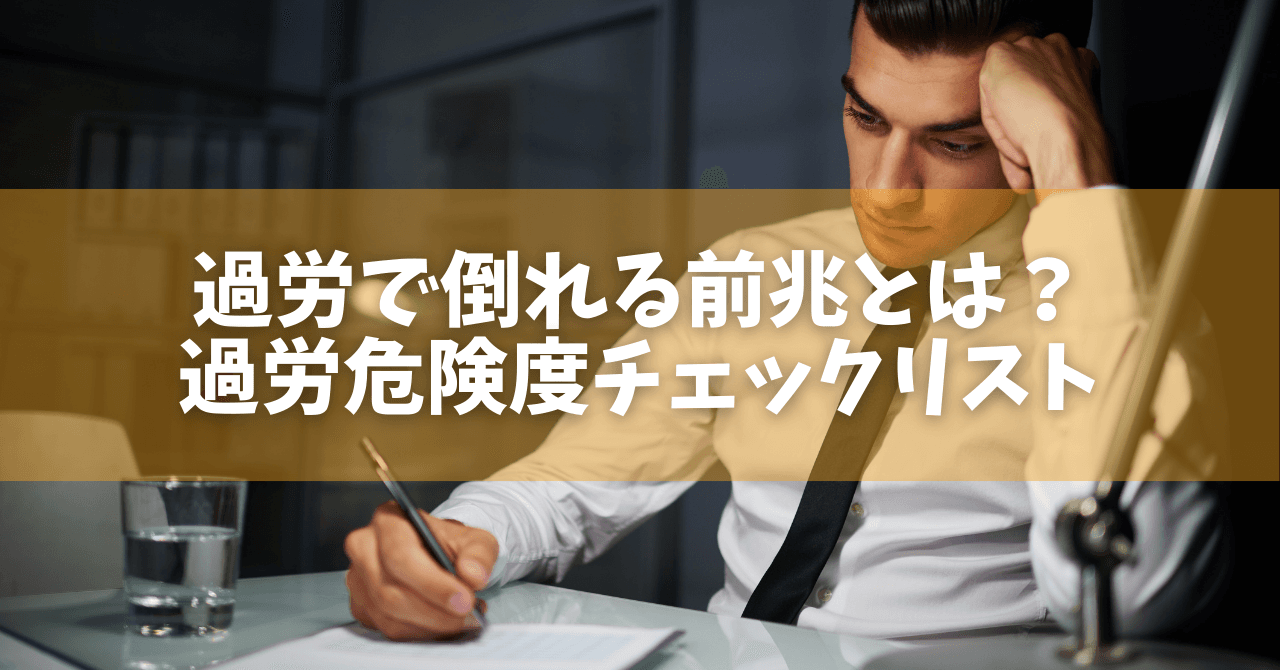
2014年11月に「過労死等防止対策推進法」が制定され、過労によるうつ病等の精神疾患、またそれらによる自死等についても「過労死」であるという新たな過労死等の基準が定められました。
過労死等を防ぐためには働く人一人一人が自分の心身の健康管理に気を使うだけでなく、企業側(経営者・管理監督者)が社員の状態をよく把握しておく必要があります。
ここでは過労状態をチェックするために知っておきたい「過労で倒れる人によく見られる前兆」をまとめてみました。 自分だけでなく会社全体にこのような兆候が見られていないか、よく確認してみましょう。

「過労によるうつ病」というと、気分が沈んだり落ち込んだりといった「精神的症状」を思い起こす人が多いですね。 しかし実際には過労によるストレスで自律神経を失調した人が最初に感じるのは「身体症状」であることも多いのです。
「頭痛」そして「肩こり」この2つは代表的症状となっています。 人間は痛いところを守ろうとし、無意識のうちに手をやることが多いもの。 頭や肩に手を触れることが多い人は、その部分に「症状」が出ているケースが多いのです。
過労ストレスで現れるもう一つの代表的症状が「腹痛」です。 自律神経(交感神経)と胃腸等の消化器官は密接なつながりがあるため、ストレスを感じた人はおなかが痛くなったり、便秘・下痢といった症状に悩まされることになります。
症状が重い場合には血尿が出たり、更には胃潰瘍といった別の身体的病気として現れるケースも少なくありません。
過労で交感神経が過剰に活発になると、胃酸が出なくなり、胃の働きが弱まります。 そのため過労でストレスが溜まった人では食欲が低下することが多いです。 過労によるうつ病の初期症状としても食欲の不振が見られています。
ただし人によってはストレスを解消しようと過食に走ったり・偏食的過食(ひとつのものばかりを異常に食べる)となるケースもあります。
過労ストレスによるうつ病の初期症状としては、集中力の低下も見られます。 特に多いのがいわゆる「凡ミス」。
字を間違える、電話をする筈だったのを忘れる、ありえないような忘れ物をする… このような初歩的なミスが増えてくるのです。
真面目で一生懸命な人ほどこのような凡ミスをしたことを恥じたり悔やんだりし、余計にストレスが増加していくことになります。
過労によるうつ病の初期症状としては「睡眠障害」も挙げられます。 布団に入ってもなかなか寝付けない、眠ってもすぐに目が覚める、寝覚めが悪い…
そもそも過労であるので睡眠時間が短い上にこのような睡眠状態が続くため、日中に頻繁に眠くなってしまうのです。 特に会議中・ミーティング中等に眠気が出る人が多く見られています。
過労でストレスが蓄積された人によく見られるのが「他人に対する余裕の無さ」です。 今までであれば受け流せた齟齬や冗談等にもひとつひとつイライラしたり、他人の欠点ばかりが目に付くようになります。
そのため職場でも衝突が増えたり、トラブルとなることもあるようです。
過労でうつ病となった人、また過労によって脳や循環器に異常が生じている人によく見られるのが「手足の痺れ」です。 特に手については痺れを感じる前に、まず物を落とすことが増えます。 手が震えて字がうまく書けないケースも多いようです。
また何も無いところでつまづいたり、ドア等に肩をぶつけるといったバランス感覚の不調を訴える人もいます。
最も心配をしなくてはならないのが、既に過労による体調不良の症状が重くなり、内科医等を受診している場合です。 過労を原因としたうつ病による身体症状の場合、原因が特定できず「疲れが溜まっているだけ」とされてしまうこともあります。
本人も「医師がそういうのだから」と納得してしまい、過労状態をさらにガマンしてしまうことも多いのです。 身体症状が既に見られており、なおかつ内科医等で原因がわからない場合には、心療内科・精神科といった心の病気の専門医を受診することが大切です。
メンタルヘルスに強い産業医と提携した企業であれば、まず産業医の面接指導を受けるのも良いでしょう。
過労で倒れる8つの前兆はいかがだったでしょうか。 思い当たる点が多い人については、早めに企業内の窓口や産業医、または外部機関への相談を考えてみましょう。 過労での休職・退職となったり、最悪である「過労で倒れてしまう」という結果とならないよう、早めに対策を行うことが大切です。
多くの悩みをサポートしてきた実績をもとに、一人ひとりに寄り添い、組織の生産性向上につなげます。
カウンセリングをベースに、コーチングやメンタルヘルス研修まで幅広いご支援が可能です。
えらべる:2つのカウンセリング方法「話すカウンセリング」「書くカウンセリング」
みつかる:220名以上の経験豊富なカウンセラー
利用された方の多くが、カウンセリングの内容に満足、または継続したいとご回答されています。