更新日 2025年06月02日 | カテゴリ: 感情をコントロールしたい
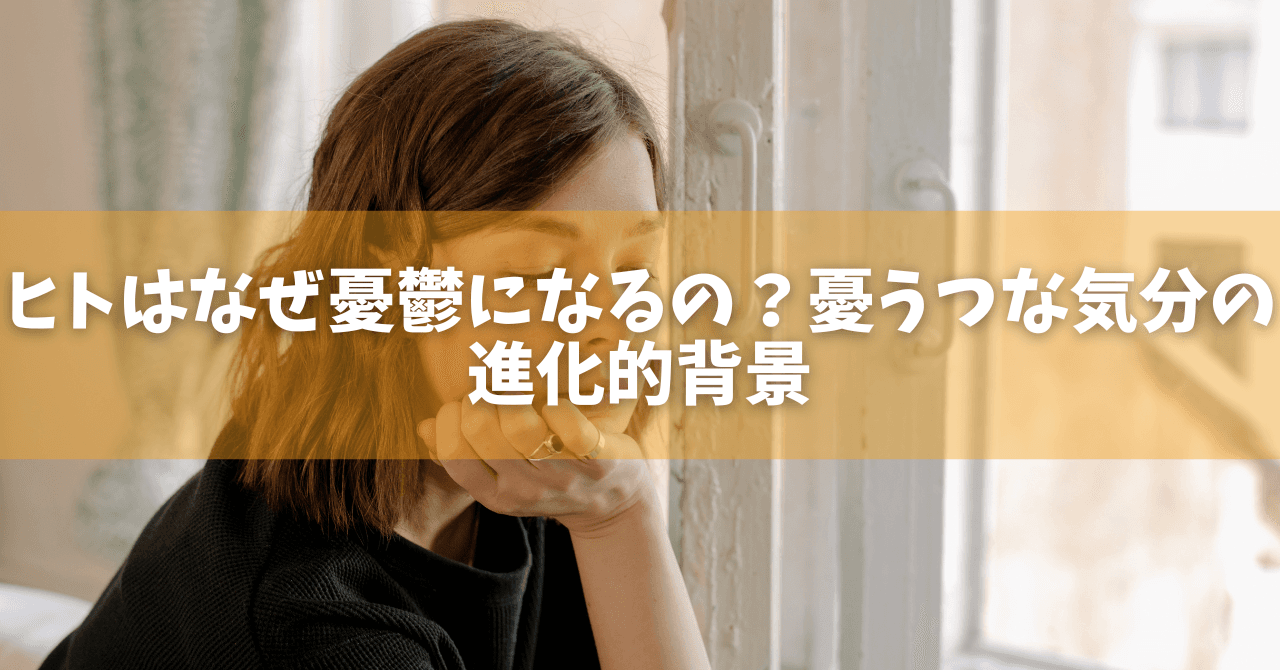
「人はなぜうつ病になるのか」という問いには、いくつかの答え方があります。 どういう生理的メカニズムでうつ病になるのか?という問いには、遺伝的要因に加えて、環境的要因・身体的要因によるストレスが重なると、脳内に変化が起こり、うつ病を発症する、と答えることができます。
今回はそのような視点ではなく、そもそも人はなぜ憂うつな気持ちを持つように進化してきたのか、という疑問に答えてみましょう。
進化生物学の観点から言えば、ヒトが様々な感情を抱くようになったのは、その感情を持つことがより高い生存率につながったからであると言うことができます。
喜びを感じることで、適応行動を起こすエネルギーになる。
愛情を感じることで、社会生活を営むことができ、子育てをすることができる。
不安を感じることで、不確実な未来に備える行動をとることができる。
では、意欲を低下させ、行動の頻度を下げてしまう憂うつさはなぜ進化したのでしょうか?
これについてはいくつかの学説があります。
憂うつになることは、不適応行動を継続していたときに「今の行動を停止する」「これまでの行動を見直し、それを棄却する」「新たな行動を始める」という結果を生むことから、人が進化するうえで必要な感情として残った、という説です。
社会的ヒエラルキーがある動物では、遺伝子を残した後には意欲低下することで世代交代を円滑に行うことができることがあります。ボスの座から降りたボスザルがまるでうつ病のように元気をなくす現象は、人間社会で退職後のうつ病が多く「地位が脅かされたとき」に生じやすいことからも裏付けられます。
憂うつになることにより、ヒエラルキーの上位からの攻撃を受けることを避けることができるという説です。
憂うつな状態を見た周りの人々は、なんとか援助の手を差し伸べたいという気持ちになるものです。動物は様々な理由で生存のための行動が困難になったときに、他の個体からの援助を引き出す行動パターンを持っており、そのうちのひとつが憂うつさであったという説です。
つまり憂うつさは「新たな生き方を導き」「争いを避け」「周囲の援助を引き起こす」ことができたために、進化してきた可能性があるのです。
これはあくまで憂うつな感情が「なぜ進化してきたか」という説明にすぎず、個人がそのときになぜ憂うつになっているのか、を説明するものではありません。しかし重要な点は、憂うつな感情が生まれていることには理由があるということです。
憂うつな気持ちを持ったときには、その憂うつさが自分にとって持つ意味を考えてみましょう。このままの考え・行動・生活を続けていると危ないという体からのサインではないですか?少し休む必要があるのではないですか?自分が大切なものを大切にしていますか?欲しいものは何ですか?誰かの助けを必要としているのではないですか?
憂うつさは、今までの考え方・行動・生き方について、じっくり考え、見直すチャンスと捉えて、自分自身と向き合ってみることをおすすめします。
参考書籍: うつ病の真実ー野村総一郎著
メッセージを添えてカウンセリング体験を贈ることができるサービスです。
悩んでいる友人や家族に心のギフトを贈りませんか?
オンラインカウンセリングを受けてみたいけど、どのカウンセラーを選べばいいか分からない...
そんな時には、マッチング診断!
性格タイプ、相談内容やご希望に沿って、あなたにピッタリのカウンセラーをご紹介します。
えらべる:2つのカウンセリング方法「話すカウンセリング」「書くカウンセリング」
みつかる:220名以上の経験豊富なカウンセラー
利用された方の多くが、カウンセリングの内容に満足、または継続したいとご回答されています。