更新日 2024年08月20日 | カテゴリ: カウンセリング
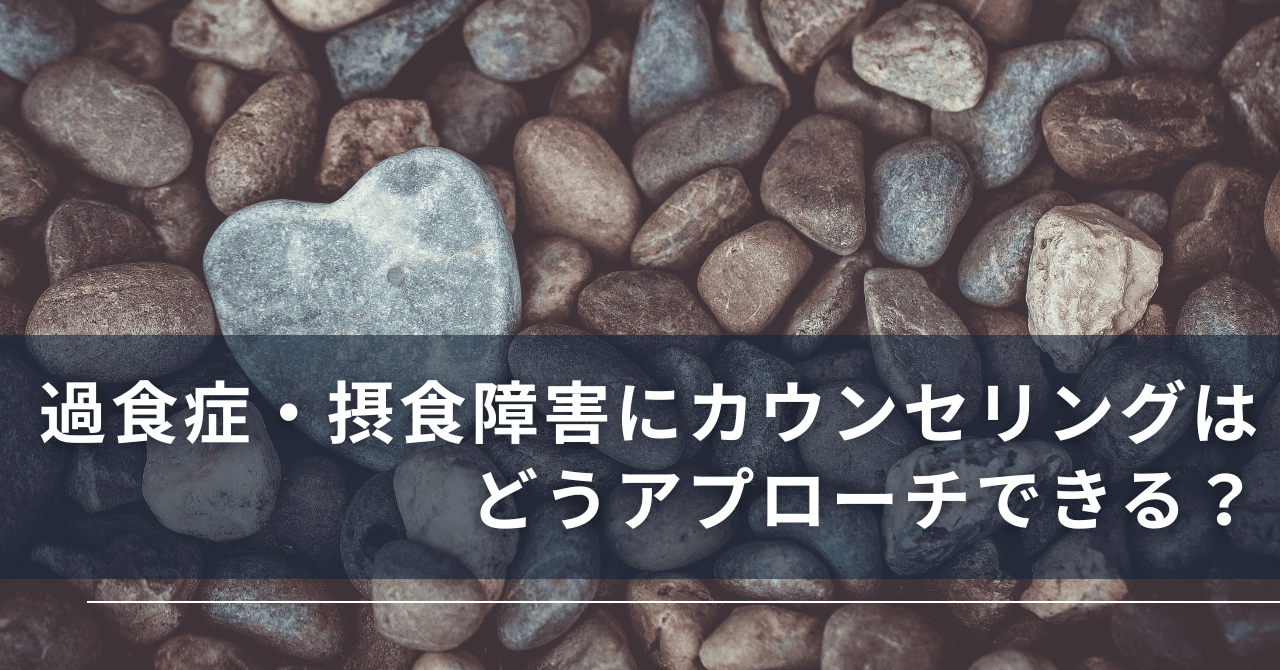
最近、中枢性接触異常症や摂食障害といった名前をよく見たり、聞いたりするかもしれません。あるいは、拒食症や過食症という名前をよく聞くことかと思います。今はそれだけ、一般的に知られており、みなさんの知り合いの知り合い、友人、親戚や家族の誰かがもっているかもしれない症状であると言えるかもしれません。
今回は特に過食症に焦点をあてて考えたいと思います。
学術的、医学的には、過食症とは「短時間に大量の食物を衝動的に食べる発作が起こる」また「自分で抑制できずに繰り返す」「大食後には後悔や自責の念にさいなまされる」(難病情報センター引用)などといったことが考えられています。
過食症が一般的で日常的なことならば、ここで取り上げる重要性はさほどありませんが、過食したい衝動が抑えられず、日常生活に支障をきたしているとなると、もしかすると「問題だなぁ」「なんとかしないとなぁ」と思いはじめる人もいるかもしれません。
過食症は専門の医療機関につながったり、栄養士さんと一緒に食事の管理をおこなったり、カウンセリングにつながったり、自助グループにつながったりと現在は色々な場所からスタートできると思います。
いつからですか?
どんな時に過食衝動がでてきますか?
どこで食べますか?
何をどれぐらい買って、どのぐらいの時間で食べますか?
食べてる時はどんな気分ですか?
食べた後はどうでしょうか?
自分が過食について、問題だなぁ、と意識したのはなぜですか?
これらの質問を読んでいると、過食をなんとか止めなきゃいけないんじゃないかと思われるかもしれません。
カウンセリングで重要なのは、過食をどうやって止めるかということよりも、なぜ過食という症状がでているのか?ということに焦点をあてて進めていくやり方もあります。
なぜ、過食を止めることだけに焦点をあてないかというと、「今まで、そして現時点では」過食行動は「その人にとって必要なこと」だと考えるからです。
カウンセリングを進めていく中で、人によっては、家族関係の話になるかもしれませんし、あるいは学校での出来事、職場での出来事、対人関係の中で体験的に繰り返されてきた、あるいは刷り込まれてきたことなどについて話しの焦点があてられてくるかもしれません。
その中で、その人自身の過食の衝動性の源になっているであろう出来事が一つあるいはいくつか見えてくるかもしれません。自分の衝動性の源となっているであろうことと向き合うことは、とても大変でエネルギーを消耗します。
カウンセリングでは、それを一人でやるよりも、信頼関係がある程度構築されている人と一緒に話し合い、気持ちを整理していくことで、「だから、自分は(私は)過食するのか」といったように、その人、その人のオリジナルな理由があり、過食行動の仕組みを自分なりに理解され、明確にされていきます。
そして、その仕組みを理解した後は、今度過食をしたくなった時に、今日は過食をする、しない、ちょっとする、今日は半分するなど、リアルタイミングで自分自身の選択肢になってくるかと思います。その選択肢を目の当たりにした時に「対処行動」をいくつかもっておくと、便利かもしれません。
自分の衝動性とどうやってつきあっていくか、ということはとても大変なことだと思います。なるべくなら、知識をもつ仲間や信頼できる人と一緒に長い目でぼちぼちやっていくというスタンスが身に付いてくると、日常生活の中で自分らしく生きていく事がもう少し楽になるかもしれません。
メッセージを添えてカウンセリング体験を贈ることができるサービスです。
悩んでいる友人や家族に心のギフトを贈りませんか?
オンラインカウンセリングを受けてみたいけど、どのカウンセラーを選べばいいか分からない...
そんな時には、マッチング診断!
性格タイプ、相談内容やご希望に沿って、あなたにピッタリのカウンセラーをご紹介します。
えらべる:2つのカウンセリング方法「話すカウンセリング」「書くカウンセリング」
みつかる:220名以上の経験豊富なカウンセラー
利用された方の多くが、カウンセリングの内容に満足、または継続したいとご回答されています。