更新日 2024年08月21日 | カテゴリ: 専門家インタビュー
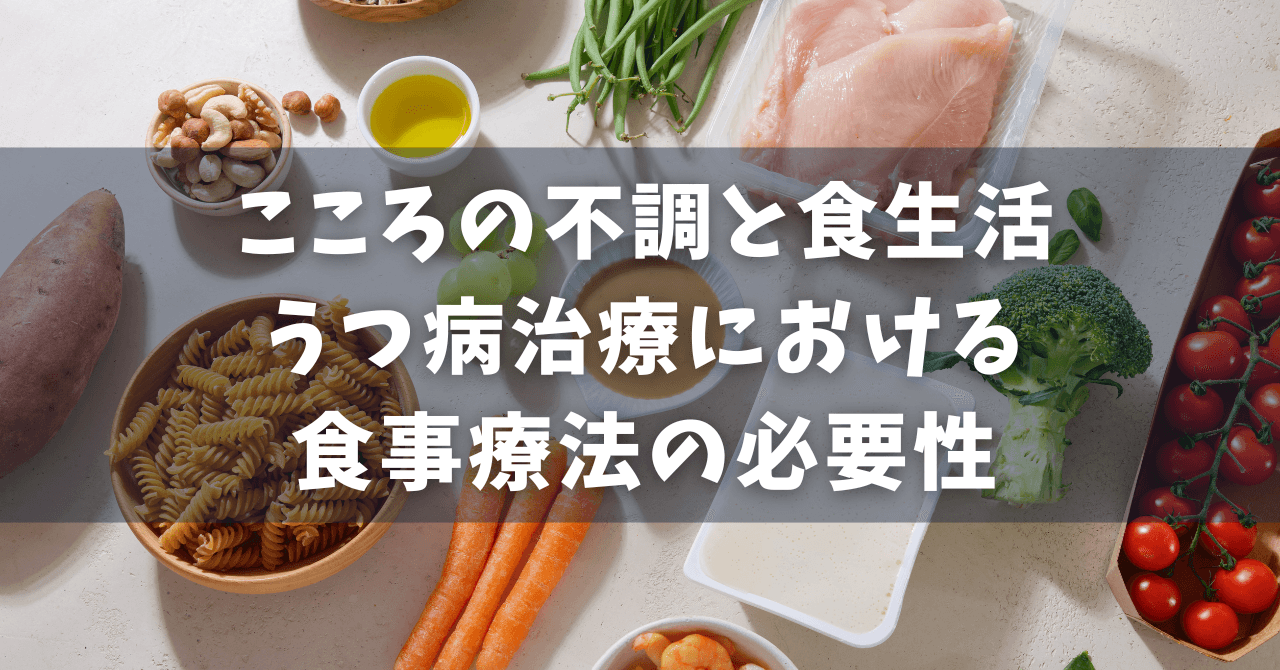
国立精神・神経医療研究センターで精神科医として研究されている功刀先生は、日本ではあまり研究されていなかったうつ病の栄養学的治療について専門的に研究され、うつ病治療における食事指導・栄養補充療法の重要性について発信しておられます。食生活とうつ病を始めとするこころの不調の関係について、お話を伺いました。
うつ病を発症する大きな要因のひとつとして、食生活の変化や運動不足、夜型生活などの生活習慣の乱れが挙げられます。うつ病は糖尿病などの生活習慣病とも双方性の関連があることがわかってきており、食生活を見直すことはうつ病治療という観点からも無視できません。
近年はうつ病と食生活に関する研究も多く行われており、特に海外ではエビデンスが急速に蓄積されてきています。食の文明化や欧米化に伴って砂糖やファーストフード・加工食品などに偏った食生活がうつ病リスクを高めることが知られています。うつ病はストレスを誘因として発症しますが、ストレスがかかると食欲が亢進し、脂肪が蓄積して体内が軽い炎症を引き起こすことがうつ病発症を促進するメカニズムとして注目されています。また、一旦うつ状態になると、運動不足や薬の副作用、食欲の亢進などによって肥満につながり、肥満がさらにうつ状態を悪化させるといった悪循環が生じます。
特に関連が指摘されるのは、葉酸をはじめとするビタミンや鉄、亜鉛といったミネラルの血中濃度が低下するとうつ病リスクが高まるという点です。セロトニン・メラトニンの原料にもなるアミノ酸であるトリプトファンや、魚に含まれるDHA・EPA、それから腸内細菌を増やすプレバイオティクス・プロバイオティクスなどについてもうつ病リスクとの関連が報告されています。緑茶やコーヒーをよく飲む人はうつ病リスクが低いという研究結果も出ていますね。
ひとつずつ栄養素やカロリーの計算をして食生活を組み立てるのは大変ですし、何より長続きしません。食習慣の改善そのものがストレスにならないように、続けられるかたちで意識しておくのが良いでしょう。
・野菜や魚・豆・果物をバランス良く摂りましょう
・糖分や加工品の摂りすぎは避けましょう
・乳酸菌飲料や緑茶を摂るようにしましょう
・バランスのとれた朝食をはじめとして三食規則正しく摂りましょう
このあたりを意識しておけると良いように思います。
一方で、どの栄養素が足りないかという点には個人差もあります。うつ病と診断されている場合には、具体的に血液検査を通じて自分に不足している栄養素を把握し、指導を受けるべきです。しかし、今のところうつ病の原因をさぐるために詳しい栄養学的検査を行っている医師は少数です。
日本ではうつ病治療は薬物療法・休養が中心になりがちですが、生活習慣の改善もひとつの柱として据えるべき要素であると考えています。また、指導を通じて数値が改善することによって自信が回復し、そこから肯定的思考につながるという効果もあるように思います。
腸内細菌叢が改善すると、視床下部ー下垂体ー副腎系のストレス応答を軽減させるという効果が報告されていて、うつ病に対する効果も期待できます。また、腸内うつ病患者の30%が過敏性腸症候群を合併するというデータがあります。過敏性腸症候群は腸内の善玉菌の減少との関連が指摘されていますから、善玉菌を増やすためのプレバイオティクス(食物繊維やオリゴ糖)やプロバイオティクス(ビフィズス菌や乳酸菌を含む食品)などの摂取を通じて腸内環境を改善することで、うつ状態の改善につながることが期待できます。
まず、研究として、ボランティア(うつ病、躁うつ病、統合失調症、健常者)を公募して血液検査や食事歴アンケートを分析し、その人に不足している栄養素や食べ方の留意点をフィードバックしています。診療では、生活習慣病を合併している精神科患者を対象として栄養管理室の管理栄養士による栄誉指導を積極的に受けてもらっています。それぞれの体質や生活に合った食生活がありますから、一般論をそのまま受け入れるのではなく、個別に指導を受ける意味があると思います。
うつ病と診断したときに詳しい栄養状態を検査する医師はまだ少ないと思います。また、栄養指導を行う管理栄養士は精神科クリニックにはおりませんし、大きな病院でないと栄養指導を受けることはできません。さらに、そうした病院であっても栄養指導は主治医がオーダーしないとできません。
だからこそ、きちんとデータを蓄積し、医師に対して発信していくことが大切だと思っています。まだまだ研究としては始まったばかりですが、数年前と比べると食事指導の重要性を理解している医師は増えていると思います。
<cotree事務局より>功刀先生の研究室では、うつ病、躁うつ病、統合失調症あるいは健常者を対象として、研究のための栄養学的検査に参加してくださる方を募集しています。血液検査と質問紙調査を受けると、分析結果を受け取ることができますので、興味のある方はぜひお問い合わせ下さい。参加は無料で、参加者の負担軽減のための商品カードをもらえます。
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 神経研究所疾病研究第三部
042-341-2712 内線5834 担当 古賀
詳細はこちら
メッセージを添えてカウンセリング体験を贈ることができるサービスです。
悩んでいる友人や家族に心のギフトを贈りませんか?
オンラインカウンセリングを受けてみたいけど、どのカウンセラーを選べばいいか分からない...
そんな時には、マッチング診断!
性格タイプ、相談内容やご希望に沿って、あなたにピッタリのカウンセラーをご紹介します。
えらべる:2つのカウンセリング方法「話すカウンセリング」「書くカウンセリング」
みつかる:220名以上の経験豊富なカウンセラー
利用された方の多くが、カウンセリングの内容に満足、または継続したいとご回答されています。