更新日 2024年08月25日 | カテゴリ: 人間関係を良くしたい
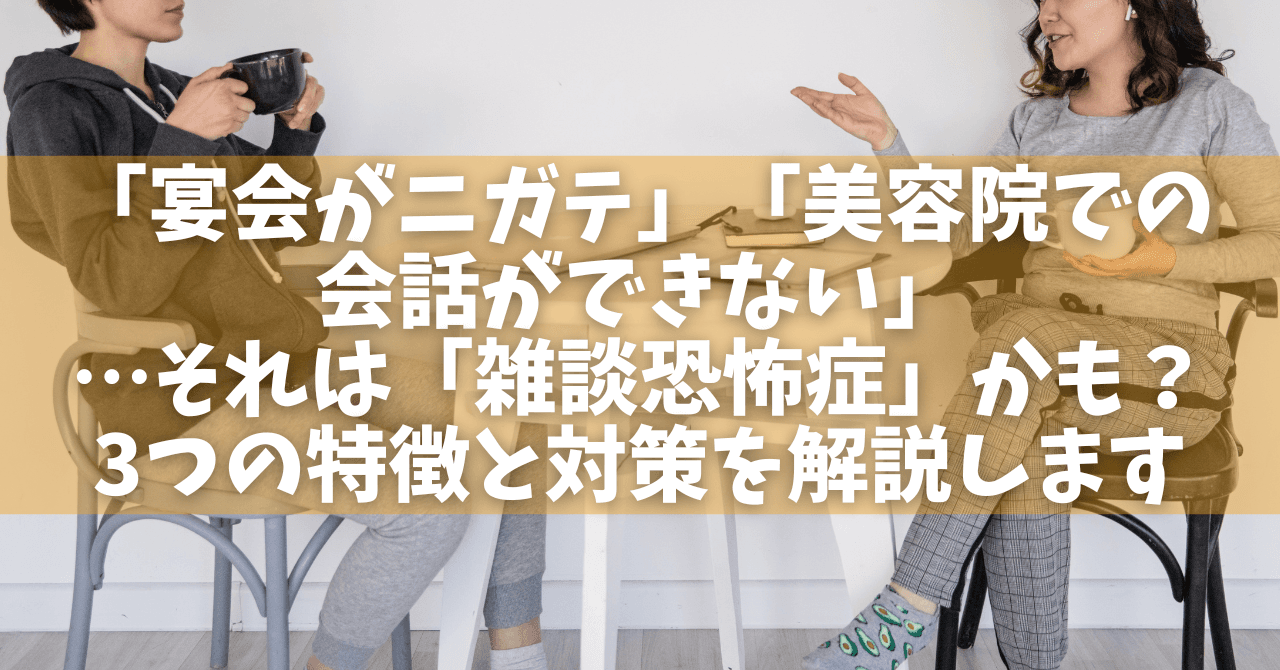
「忘年会や新年会で隣り合った人と何を話したらいいのかわからなくて、宴会の時期になると憂鬱」 「美容師さんと会話をするのがニガテで、美容院に行くのすらイヤ…」 天気の話やレジャーの話といった、いわゆる「雑談」と呼ばれるものが極端に苦手という人、意外と多いですよね。
最近では上手に話ができない人のことをネット用語で「コミュニケーション障害(コミュ障)」と呼び、自分のことを「コミュ障で…」と自称する人もいるようです。
しかし、雑談に対して多大な苦痛を感じ、社会生活にも支障が出るといった場合、それは「雑談恐怖症」である可能性もあります。 今回は「雑談恐怖症」について、その特徴や対策をご紹介していきます。
「雑談恐怖症」は、社会不安障害である「対人恐怖症」の一種です。 対人関係の「雑談」という場において過剰な不安、自信の喪失を憶え、雑談の場を過剰に遠ざけたり、相手との距離を必要以上に取ることもあります。
雑談恐怖症の最も顕著な特徴が、「中身のある会話」は可能であるという点です。 例えばビジネスシーンでの伝達事項等はごく普通に行うことができるという人がほとんど。
また共通した趣味を持つ仲間との情報の共有、有益な情報の交換等はスムーズにできるという人もいます。
雑談恐怖症となる人の多くは、相手の表情や態度等のノンバーバルコミュニケーション(非言語的な表現)を非常によく観察しています。 いわゆる「場の空気を読めない人(KYな人)」ではない、というわけですね。 反対に「場の空気を読みすぎてしまう(気にしすぎてしまう)」というのが問題なのです。
元来、日本文化においては「その場の調和」を重んじる傾向があり、自己の自由な発言よりもその場を盛り上げること、場を和ませることが重要視されてきました。 「楽しい雰囲気を作らなくてはならない」「場に馴染まなくてはならない」という緊張やストレスが、ますます雑談を苦手とさせていることも多いのです。
「元々は雑談がそこまで苦手ではなかった」という人でも、進学・就職等で新たな集団に加わったり、新たな人間関係を築く際に、雑談の場でつまづいてしまうことがあります。 「話し方を笑われた」「うまく話せずに周囲から弾き出された」などの失敗体験が自信を喪失させ、「自分は話し下手だ」「誰ともうまく話せない」という自己暗示をかけてしまうことも多いのです。
雑談恐怖症となりやすい人の多くが、雑談をする際の理想のハードルを非常に高く設定しています。 テレビや周囲の会話等からキャッチした「もっとも話し上手な人」が標準的であると感じ、「同じように話さなくてはいけない」と考えてしまっていることもあるのです。
まずは自分が話す内容について、「盛り上げよう」「笑いを取ろう」「結論を付けよう」という力みを取ることから始めてみましょう。
「雑談が苦手」という人のほとんどは「話題を提供できない」ということに悩みがち。 たしかに話し上手な人は色々な経験をされていて、面白い話を繰り出してきますよね。
でも雑談に加わるには、けして「話題提供者」になる必要は無いのです。 会話の発端は「相手への質問」から始め、相手の回答に対して興味や同意を示せば、話題は相手が広げていってくれます。
人は自分の話に耳を傾け、興味を持って話を聴いてくれる人に好感を持つものです。 ムリに「話そう、話そう」と考えるのではなく「良い聞き役になってみよう」とする意識を持つことで、雑談への姿勢も変わってきます。
「話しが下手だから、雑談ができない」と考える人の多くが、「上手な話題の引き出し方」といった、いわば「話し上手になる技術」的な問題に着目し、問題を克服しようと努力されています。
しかし雑談恐怖症の根本的な解決は「技術力」ではありません。 大切なのは、「コミュニケーションが苦手だ」という強い思い込み(認知の歪み)を捨てること。
そしてもうひとつが「相手に合わせた会話をしよう」と相手の反応を過剰に重視する姿勢を捨て、自分が感じ、考えたたことを自然に外に出せるようになることです。
とは言え、自分の今までの感じ方や考え方(認知)を自分一人で改善するのは難しいもの。 こんな時にはカウンセリングを受けてみるのも手です。
「雑談恐怖症」の治療では「認知行動療法」等の療法を行い、物事の受け止め方、感じ方等の再評価を促していきます。 心のケアを専門家と共に行っていくことが、リラックスしたコミュニケーションへと繋がっていくのです。
「雑談恐怖症」の症状が重くなると、会社等での人間関係に問題が生じたり、生活に必要な行動が起こせなくなるほど、社会生活に大きな支障を伴うことも。
また「雑談恐怖症」を始めとした対人恐怖が、ニートや引きこもり等の原因となることもあります。 既に生活での支障を感じている場合には、早めに専門家への相談をしましょう。
メッセージを添えてカウンセリング体験を贈ることができるサービスです。
悩んでいる友人や家族に心のギフトを贈りませんか?
オンラインカウンセリングを受けてみたいけど、どのカウンセラーを選べばいいか分からない...
そんな時には、マッチング診断!
性格タイプ、相談内容やご希望に沿って、あなたにピッタリのカウンセラーをご紹介します。
えらべる:2つのカウンセリング方法「話すカウンセリング」「書くカウンセリング」
みつかる:220名以上の経験豊富なカウンセラー
利用された方の多くが、カウンセリングの内容に満足、または継続したいとご回答されています。