更新日 2024年09月03日 | カテゴリ: 職場のメンタルヘルス
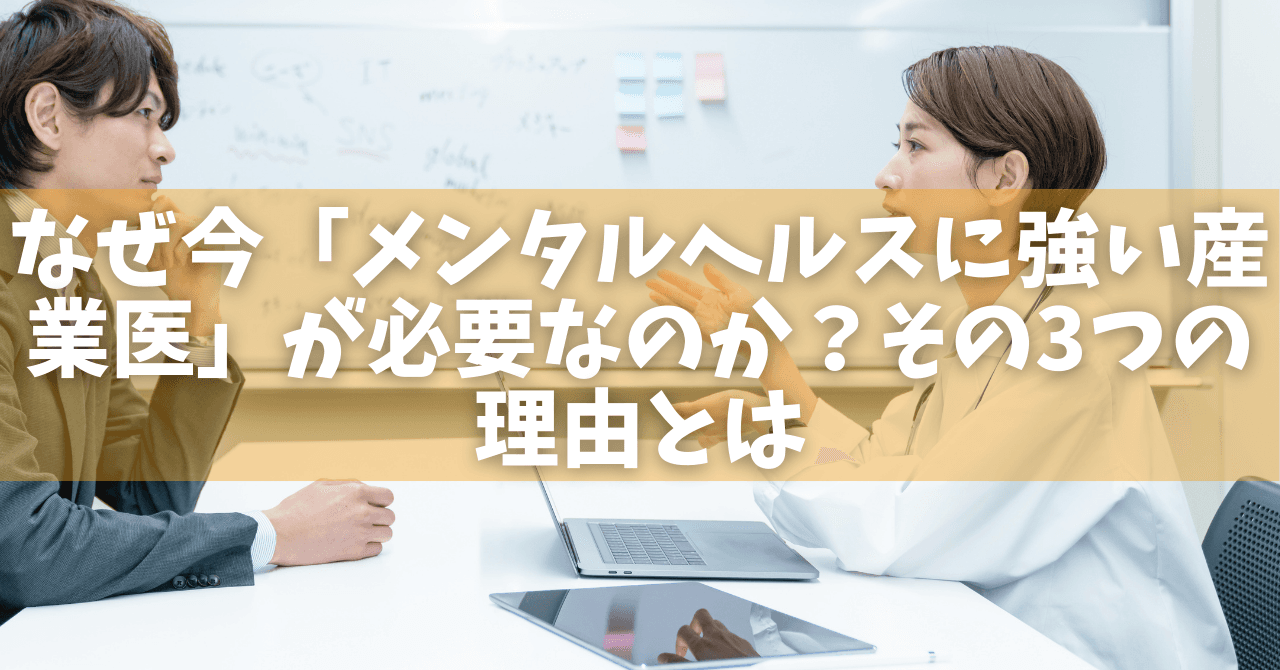
「産業医」とは企業内に配置、もしくは企業と提携をする形で従業員の健康管理・指導を行う医師のこと。 2015年に施行開始された改正労働安全衛生法で、企業におけるストレスチェック制度が義務化されたことから、産業医に対する注目度は急速に高まっています。
しかし産業医のメンタルヘルスケアにおける役割は、年に一度のストレスチェックを行うだけではありません。 ここでは3つの側面から、現代企業においてメンタルヘルスケアに強い産業医が望まれる理由を解説していきます。
法律の改正によって、企業におけるメンタルヘルスケア対策の推進レベルには益々高いものが望まれるようになっています。 多くの企業が取り組んでいるのが、以下のような対策です。
従業員一人一人がメンタルヘルスについての基礎知識を持ち、自分の心身の状態を正確に把握して管理できるようにする。
上司・リーダーが部下の悩みやメンタル問題をサポートできるように情報を与え、実践的研修を行う。
心身の不調について、またパワハラ・セクハラ・モラハラ等の悩みについて従業員の不満や不調に対応できる窓口を設置する。一次対応は社内担当者が行い、必要に応じて二次対応・専門対応への引き継ぎを行う。
上記のような対策をメインで行うのは、主に人事・総務スタッフ等から選出されたメンタルヘルスケア対策の担当者であるという企業が多いでしょう。
しかし担当者にとっても、身体の不調ではなく「心の不調」を取り扱うのは初めてであるはず。 不明点や疑問点が多く、対策をなかなか進められないケースが少なくないようです。
産業医や産業カウンセラー等の保険スタッフは、このような企業内メンタルヘルスケア対策についての助言・指導を行ってくれます。 またラインケア研修・セルフケア研修等も保険スタッフが請け負う提携機関も増えています。
うつ病や気分障害といった「心の病気」も、身体の病気と同様に早期的な対策を行うことが大切です。 ところが心の病気の場合、当人の自覚や周囲の気付きが身体不調に比較して無い、遅いという問題があります。
例えばうつ病の場合、あらわれる症状が「気分の落ち込み」「死にたいと思う」といった精神的なものだけと思っている人が多いのではないでしょうか? 実際にはうつ病の初期症状では、慢性的な下痢や頭痛、睡眠障害、胃痛といった身体症状からスタートすることも多いのです。 結果として本人も周囲も心の不調になかなか気づかず、重症化させてしまうケースが散見しています。
メンタルヘルスケアに強い産業医であれば、定期巡回・相談窓口からの二次対応・ストレスチェックの内容等から、従業員のメンタルヘルスについて早期的に適切な対応を行うことが可能です。 うつ病・気分障害等による休職・退職といった問題を未然に防ぐことで、人材の流出や退職率の上昇といった問題の改善にも繋げられます。
現在、うつ病や気分障害・不安障害等で休職をする人は全体の7%以上。 「心の病気による休職への的確な対応」は、いまやどの企業にも求められるものとなっています。
しかし当人による主治医の診断書・主治医からの回復判断を持って休職判断・復帰判断を行う企業もまだ多いようです。 この点が休職からの再度の欠勤、再度の休職を繰り返すといった問題に繋がっています。
主治医の根本的な立ち位置は「患者を寛解させること」です。 そのため立場としては患者よりになりますし、復帰の判断(寛解の判断)を主に「日常生活を送れるか否か」という点を基準とする医師も少なくありません。
ところが医師の考える「日常生活」と、実際の「勤務状況」に大きな開きがある場合、「まだ勤務ができる状態ではない」という可能性も起こりうるわけです。
そのため現在では、休職判断・復帰判断において主治医の診断書に加え、産業医による指導面談、また産業医紹介の専門医の見解をプラスする企業が増えています。 産業医は企業内の巡回や業務内容をチェックしていることから、より勤務状態を正確に把握した上での復帰判断が行えるわけです。
うつ病や不安障害・適応障害といった心の病で病院を受診する人の数は、現在も右肩上がりで増えている状態です。
今やメンタルヘルス対策を的確に行うことが、企業の発展を考える上で欠かせない要素であると言えるでしょう。
対策を的確に行うための一つの手段が「メンタルヘルスケアに強い産業医の設置」というわけですね。
会社内に産業医設置を行うのが難しい企業の場合、提携する外部機関を選ぶところからスタートするのが良い手ではないでしょうか。
多くの悩みをサポートしてきた実績をもとに、一人ひとりに寄り添い、組織の生産性向上につなげます。
カウンセリングをベースに、コーチングやメンタルヘルス研修まで幅広いご支援が可能です。
えらべる:2つのカウンセリング方法「話すカウンセリング」「書くカウンセリング」
みつかる:220名以上の経験豊富なカウンセラー
利用された方の多くが、カウンセリングの内容に満足、または継続したいとご回答されています。